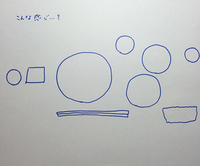「違うこと」から生まれるコミュニケーションのかたち
伊藤亜紗(東京工業大学リベラルアーツ研究教育院准教授)
21世紀の身体感覚を探る試み
今年3月、国際交流基金の主催で、「科学と文化が消す現実、つくる現実―フィクション、制度、技術、身体の21世紀―」が行われました。これは、ヴァーチャルリアリティ(VR)や人工知能(AI)などの先端技術の研究・普及によって変わりつつある〈現実〉の見え方を、5つの視察・ワークショップ・講義から考えるというものです。「ミッション・プロジェクト」という当基金内の公募企画で、日本に留学中の外国人大学院生・研究者が参加しました。その4回目の講義に登壇したのが伊藤亜紗さんです。東京工業大学リベラルアーツセンター准教授の伊藤さんは、近著『目の見えない人は世界をどう見ているのか』や、ワークショップ「視覚のない国をデザインしよう」での取り組みを通じて、目の見えない人や耳の聞こえない人がどんな身体感覚を持ち、どのように世界を把握し関係を結んでいるのかを研究しています。
伊藤さんが研究の過程で触れた様々な事例を挙げ、視覚や知覚についての講義が行われました。時に参加者との対話も交えつつ、やがて浮かび上がってきたのは、障害を持つ人、持たない人のあいだの差異だけではなく、誰もが持っている先入観や価値観の多様性、イメージのバリエーションの豊かさでした。

まずは自己紹介、場所を考える3つのワークショップ
「感覚」や「芸術」といった言葉に変換しづらいものを、あえて言葉を使って研究していく学問である「美学」。それが伊藤さんの研究領域ですが、その研究のアプローチは少しユニークです。
伊藤 研究者なので執筆や研究がメインなのですが、言葉を通じて自分のコンセプトを人に伝えるだけでは足りないと思い、ワークショップやアーティストの小林耕平さんたちとチームを組んで作品制作をしたりもしています。例えば、2015年10月に八王子で企画したワークショップ「OK-3ビルのトリセツ」では、雑居ビル内で長らく空き物件になったままの一室を活用する方法を、3つのアプローチから検討しました。その物件には、キャバクラ、レゲエバーなどが入居していたのですが、全部経営がうまくいかず、その失敗の空気がどんよりと溜まっているようでした。その独特の空気感は、数値化したり、言葉で分析するのが困難な類いのものですが、その感覚的な要素をワークショップで扱えないだろうか、と思いました。

八王子で企画したワークショップ「OK-3ビルのトリセツ」について語る伊藤さん

「OK-3ビルのトリセツ」のチラシ
そのワークショップに、伊藤さんは3人の研究者を招きました。1人はアーティストの橋本聡さん。いまは東京の都心の文化が西の端である八王子に伝播するという方向ですが、江戸時代にはむしろ八王子は上方の文化が入ってくる玄関口で、文化が東に向って伝播するという話を聞いて、方位という観点から八王子をとらえたら面白いのではないかと考え、テーマに選んだのだそうです。
2人目は、生物学者の山田拓司さんに、腸内菌について話していただいたそうです。体重70kgの男性の場合、そのうちの約3kgを占めることもあるという菌は、その性質によって人間の体臭を決定するほど人体に大きな影響を与えています。その人の体臭と生活する部屋の匂いが似通うことは多くありますが、それも菌が影響しているらしく、この空き物件でかつて働いていた人たちについて、菌を通して考えようとしたのだそうです。
3人目は闇学の中野純さん。三途の川で死者の衣服を奪う奪衣婆(だつえば)という妖怪がいますが、この講義では、昔の人たちがある場の特性を、妖怪といった超自然的な存在に仮託して捉えていた伝統や思考様式について考えました。
この変化球的な3つのレクチャーを踏まえて、空き物件の実際的な活用法を考えるワークショップを行ったそうです。奇抜にも思える問いを仮説的に立てることで、これまでとは異なる発想や見方を発見するという考え方は、現在の伊藤さんの活動の一面を示しているといえるかもしれません。
抽象化された身体から、個別の身体へ
伊藤 最初に、障害についての私のアプローチを説明しておきましょう。一般に障害についての研究というと、福祉のイメージを持たれるのですが、私はあくまで身体論として障害を考えています。福祉の最終的な目標は、例えばバリアフリーのように障害者も健常者も等しい生活ができる社会を実現することと言えます。福祉的なアプローチはもちろん大切なのですが、それでもやはり残る違いに注目したいと考えています。例えば、目の見える人が周囲の様子を目で見ながら駅まで行くのと、目の見えない人が点字ブロックを使って駅まで行くっていうのは、行動としては同じでも、実際の経験としては相当違います。

伊藤さんは身体論として障害を研究
かつて伊藤さんは、50代の中途失明の男性に駅から自宅までの道のりを文章で説明してもらったことがあるそうです。その人物は「(通りを)横断したら、そのまま道なりに歩道を100mほど直進、途中右手からウナギ屋さんの匂いがしてくる。さらに進むと豆腐屋さんの匂いがしてくる」といった風に道程を記述していました。それは視覚以外の感覚で把握できる要素を目印(鼻印?)にして、各ポイントを辿っていくような街の理解の仕方と言えるでしょう(そのため、自分がポイントにしているものをキャッチできないと、自宅の近所でも迷子になってしまうことがあると言います)。
伊藤 通常、健常者の身体が完成形で、障害者はそこから何らかの機能を引いたものとして捉えがちです。でも、身体というのは周囲の環境との関わりの中で、固有の意味を発生させるものです。19世紀に生まれたエストニアの生物学者ヤーコプ・フォン・ユクスキュルは、それぞれの生物が把握している固有の世界認識を「環世界」と呼びました。同じお花畑でも、人間と比較すると、蜂は蜜を持っている花だけが浮き出して見えるような認識をしているかもしれない。つまり、異なる身体的特徴を持つ生物のあいだでは、環境の見え方、意味が変わってくるはずだと推測しました。
一般的に文系の学問は、人間の身体を前提にして研究していますが、それは非常に抽象化された人間像です。実際には、男女、年齢、運動神経など多くの違いがあって、それぞれに異なる世界認識をしているはずです。それを考えるために、私は一番違いが見えやすい人として、障害者の皆さんとワークショップや研究を続けているんです。

環境によって固有の意味を生じさせる身体ついて語る伊藤さん
研究を続ける過程で、伊藤さんは視覚障害者の世界の見方に3つの方法があることに気づいたと言います。ひとつ目は、触覚や聴覚など、視覚以外の感覚。2つ目は白杖やスマートフォンの音声アプリといった道具を使うこと。3つ目は、周りの人と周囲の状況について話して、世界を認識する方法です。
世界を知覚する3つの方法
視覚以外の感覚というと、触覚でものの位置を把握したり、音の反響具合で壁があることを知るというような「見方」が思い浮かびます。そうしたことは、見えない人にインタビューするなかでいろいろと見つかるそうですが、見えない人の「見方」を、見える人に分かるように「翻訳」する作業は、いつもスムーズに行くわけではないそうです。 伊藤さんは、先天的に全盲の方とランチをした際のエピソードを紹介しました。
見え方によるてんぷら定食の認識の違いをスライドで解説。
伊藤 先天的に全盲の方は「見る」という経験を持っていません。したがって、さまざまな物をいっさい視覚的な情報に変換しないで理解しているわけです。これは見える私たちにとってはなかなか想像のおよばない領域です。そのとき、見た記憶のない方と天ぷら定食を食べていました。いろいろ話を聞いてみると、その人はお椀や皿がたくさん乗っかった天ぷら定食を「パソコンのデスクトップ」として理解していました。ごはんや小鉢はそれぞれがアイコンで、クリックするかのように箸を向けることで、エビ天といった、詳細が分かるんですね。目の見える人は視覚から一瞬にしてかたち、種類など様々な情報を受け取りますが、視覚障害者は行動するうえでとりあえず大事な位置情報を把握してから、「コンテンツ」というより深い階層の情報にアクセスしていく。普通に見えている人には分離することのできない情報の整理方法を持っているのではないかと思います。
2つ目の道具を使う。ここでは「Be My Eyes」という視覚障害者を支援するSNSアプリを紹介しました。これは見えない人が被写体を撮影することで、見える人がそれが何であるかをライブに応えてくれるというものです。
伊藤 スマートフォンの登場以降、視覚障害者はアプリを多く活用しています。「Siri」などの人工知能、音声読み上げソフトはその代表的なものですね。目の見える人は「見る」ことと「読む」ことを同時に行うのでなかなか気づきませんが、音声アプリを介する場合、視覚障害者にとっての「読む」ことに自動音声という新しい項が加わり、情報の理解のプロセスが複層化するんです。
3つ目の会話によって世界を認識するとは、「言葉で見る」と言い換えることもできるでしょう。
小学校の音楽室に飾られている有名音楽家の肖像画を覚えている人は多いでしょう。そこにあるベートーベンの肖像に対して、ある視覚障害者の人は独特の感覚を持っているようです。
伊藤 その人は小さい頃に光を失っているので、ベートーベンの肖像画は見たことがないのですが、それでもそれが厳めしい顔をしているのは知っていました。なぜかというと、周りの子たちが学校の怪談として「夜中に目が光った」「こっちを見ていた」といった話をしていたからです。つまり周囲の情報によって、彼の「見えた」経験がかたちづくられたわけです。
この話には面白い挿話があります。ご存じの方もいるかもしれませんが、実際のベートーベンはそんな厳めしい顔をした人物ではありませんでした。けれども彼が活躍した19世紀は、芸術家は特殊な能力を持ち、一般の人とは全然違う世界に生きた天才である、という価値観が強固にあった時代でした。そのためにある意味で狂気じみた雰囲気の肖像が広く一般に受け入れられたんですね。ここには、「見る」ということがあらゆる人にとって一様ではないという事実があると思います。自分自身が見たもの=正しいと私たちは理解しがちですが、そこには「こうであるはずだ」という無意識の思い込みが前提として強く存在しているんです。
多くの視覚障害者は、「見えることが正しい」という先入観を持っています。「常に正しいわけではない」という見える世界の状況も、見えない人に伝えるべきだと思います。
別の言い方をすれば、視覚障害者は客観的に見える視覚的な情報だけではなく、そこに込められた社会的な意味や価値づけを見たいと思っている、あるいは「見ている」とも言えるのではないでしょうか。
障害が触媒になり、議論が深まる
伊藤さんが注目している取り組みのひとつに伊藤さんが「ソーシャル・ビュー」と呼ぶ美術鑑賞のスタイルがあります。これは目の見える人と見えない人で8人くらいのグループをつくり、美術鑑賞を行うという試みです。そして絵画に描かれている要素を言葉にして説明し合います。

ソーシャル・ビューの様子(視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップより)
伊藤 たとえば横尾忠則さんの《花嫁》という作品についてソーシャル・ビューを行ったときのこと。画面の中央に角隠しをかぶった女性が描かれているので、最初は「美人である」といった普通の感想が出ます。ですが、次第に見る人それぞれのバックグラウンドが露わになるようなコメントが出てきます。例えば親指と人差し指でチョキをつくることを「男のチョキ」というらしいのですが、これは昔の関西圏で生活した人にしか伝わりづらい表現なんだそうです。そのようにして、それぞれの違いを認識しながら、共同作業として結論に行き着くというのが、ソーシャル・ビューの一つの目的なんです。
もう一つの例として伊藤さんは、アメリカの画家ジャクソン・ポロックの作品を理系の大学生たちに授業で見せた際の経験を紹介しました。抽象表現主義の代表的作家で、即興性を兼ね備えた「アクション・ペインティング」という手法で美術史に名前を残すポロックですが、理系学生にはあまり評判がよくありませんでした。
伊藤 理系の学生の大半が、ポロックの絵画に「汚い」という印象を抱くんです。もう少し詳しく聞いていくと、どうやら「子供の落書きのよう」=「技術が欠如している」=「再現性がない」ことが、ネガティブな印象を持たせる主要な理由のようでした。
つまり、今日やった実験が、何年か後にまったく別のところで別の人物がやったとしても再現できることが理系の研究としては重要であり、ポロックや現代のアーティストたちの多くが重視する「一回性」や「今ここ」的な現前性は、理系学生にとっては不可解なものとして「見える」わけです。近年話題になったSTAP細胞のように、再現性のないものは価値がないんですね(笑)。
ここでもう少しひねった議論を続けました。「逆に再現性がないけど価値のあることは何か?」。この問いかけの末にたどり着いたのはスポーツです。例えばサッカーの試合は一度きりのもので勝敗が決するからこそ熱狂できるし、競争の公平性が保たれる。そういうユニークな見方を導入すると「ポロックのアクション・ペインティングはスポーツである」という、どの美術書にも書かれていない結論にたどり着いたりする。これもソーシャルビューならではの楽しみ方ですし、参加者の人間関係を深めていくような働きもあるのがわかると思います。
この後、ロシアの画家カジミール・マレーヴィッチがサッカーを主題に描いた《フットボールの試合》を題材に、講義参加者も加わって即興的なソーシャル・ビューを行うなど、実践も差し挟みながら伊藤さんの講義は進んでいきました。
伊藤 ソーシャル・ビューにおいて大事なのは、解釈を楽しむ局面では、見える/見えないは関係ないということです。例えば誰かのユニークな解釈によって全体の見え方の意識ががらりと変わると、その変化は視覚障害者も共有できる。
どんな人も先入観なしに見ることはできないので、自分の知っているパターンに当てはめることで最初は対象を理解しようとします。でも、見れば即座にわかる色やかたちをあえて言葉にすることで、見える人、見えない人それぞれが共有できる議論の場の雰囲気が生まれ、「みんな(物の見方が)相当違うよね」ということを自然と共有できるんですね。
そういう意味で障害が触媒となって、当たり前に共有していると思っていたことが、じつは共有されていなかったということが露わになるわけです。障害が入ることで、その場の活性が一層高まる。そうやって障害が重要な役割を果たしていくところが、すごく面白いところだと思っています。

伊藤亜紗さん(中央左)、企画監修・ファシリテータの西川アサキさん(中央右)と参加した外国人大学院生・研究者の皆さん
*本プロジェクト受講者によるレポートの一部を公開しております。
(編集:島貫泰介/講義の写真撮影:石川幸史)
伊藤 亜紗(いとう あさ)
東京工業大学リベラルアーツ研究教育院准教授。専門は身体論、現代アート。著作に『目の見えない人は世界をどう見ているのか』(光文社)ほか。研究のかたわら、作品制作やワークショップのプロデュースにもたずさわる。