関連記事
関連キーワード
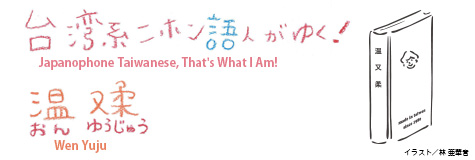
9.散歩は、おとなの証拠とばかりに・・・・・・
「台北市立美術館(Taipei Fine Arts Museum)」といえば、台北ビエンナーレの本拠地として大変有名な美術館ですが、長いあいだ私にとっての「台北市立美術館」は、夜、私たち家族のために叔父が走らせる車の窓から眺める白い壁のことでした。ライトアップされた光の中に白いその壁が浮かびあがるたび、うっとりとさせられました。
「台北市立美術館」に限らず、私にとっての"台湾"のさまざまな風景は、空港から祖母や親戚の家に行く途中の車の窓から眺めるものでしかありませんでした。もちろん近所を出歩くことはあったけれど、いつも両親や親戚のだれかに連れられているような状態でした。要するに、自分ひとりであちこち歩き回る機会はめったになかったのです。そうしようと望んだとしても、母が決まって私を制します。
――迷子になったらどうするの?
実際、私は7歳だか8歳のときに祖母の家の近所の駄菓子屋にひとりで出かけたのはいいものの帰り道がわからなくなり、台湾語も中国語もうまく話せず、あまりの心細さに泣きじゃくっているところを探しに来てくれた叔母のおかげで難を逃れたという苦い過去があります。
子どもの頃、迷子になった祖母の家の近くで。
おとなになった今、台湾――ここ数年は主に台北であることが多いのですが――滞在中は、暇さえあればひとりで散歩に出かけます。
といっても、特に厳密な目的地は決めません。今日はこのエリア、明日はあのエリア、という感じで歩き出すのです。
繁体字の踊る看板にわがもの顔で居座る平仮名の"の"を数えるのを楽しんだり、雑踏を行き交うひとびとの会話が本当に中国語と台湾語のちゃんぽんであることを面白がりながら懐かしんだり、露店で衝動買いした巴樂(グァバ)を、ガジュマルの樹の下で齧(かじ)ったり・・・・・・。
観光客としては、縁が深すぎる。住民にしては、風景のひとつひとつが新鮮で胸が弾んでしまう。そんなふうに観光客以上住民未満の心地で、台北の、台湾の街をいそいそと歩き回ることを楽しむ台湾系ニホン語人なのです。
日本では食べられないので、台湾に帰ったら真っ先に食べたいのがグァバ! ジュースになったのも大好き。
そんなふうにして何となく行きつき、魅了された場所がいくつかあります。
真っ先に思い出すのが、「光點台北・台北之家 (SPOT Taipei Film House)」です! こんもりと繁茂するガジュマルの樹々の中にあるケーキのような形の洋館は、約40年前まではアメリカ大使館邸として使用されていた屋敷でした。「光點台北・台北之家」は台湾ニューシネマの巨匠、侯考賢プロデュースによる映画がテーマのアートスポットです。
ミニシアターではレアな映画をしょっちゅう上映するのもあって、映画好きの台北っ子にはたまらない場所だそう。私はどちらかといえば、1階にあるその名も「珈琲時光」と名づけられたカフェに行くのが好きです。気候のよいときはテラス席を選びます。木漏れ日の中でひと息つきながら"珈琲(コーヒー)"を飲む"時光(時間)"を堪能します。
「光點台北・台北之家」がそうであるように、台湾にはアートを軸とした興味深いスポットがたくさんあります。
たとえば、「台北当代芸術館 (Museum of Contemporary Art Taipei)」。ここは小学校の跡地を活用した空間で、"当代"という文字が示すように現代アートの美術館なのですが、元小学校である建物内の独特な雰囲気が非常に味わい深かったです。そう、次の展示室に移動するときは図画工作の授業を抜け出して廊下を歩いているような心地がするのです。
日本統治時代の古い酒造工場をリノベーションした「華山1914・文創園区 (Huashan1914・Creative Park)」にはじめて足を踏み入れたときも、中心となる建築物は重厚ながらも風通しのよい全体の雰囲気にたちまち魅了されました。展覧会や芸術活動が催されるのはもちろん、カフェやレストラン、雑貨屋などもあり、1日中楽しめます。
小学校の跡地を活用した「台北当代芸術館」もそうであるように、台湾ではここ数年、長い間使われずに放置されていた工場や廃駅などの建築物をリノベーションし、美術館や観光地に"蘇生"する動きがとても盛んだそうです。「華山1914・文創園区」は、その先駆けだといいます。"文創"とはずばり"文化創意"のことで、あらたな価値をつくり出す、という意味が込められているのです。日本統治時代に稼働していた古い煙草工場跡地を活用し文化総合施設として生まれ変わった「松山文創園区」もそのひとつです(次回の帰国時にゆっくりと訪れたい!)。
「四四南村 眷村文物館(Sisinancun Quancun Museum)」に偶然辿りついたときは、ごくふつうの古めかしい民家のたたずまいながら、妙に圧倒されるものを感じました。「眷村」とは、毛沢東との内戦に敗れた蔣介石とともに大陸から台湾に移り住んだ軍人たちの村のこと。
「四四南村」は、中国の青島出身の軍人とその家族の住まいだった建物――といっても、トタン屋根にペンキの剥げた壁が印象的な長屋のような――を文化遺産として残し、やはり"文化創意"の発想のもと、往年の歴史を記録する博物館とともにカフェや雑貨店を併設するアートスポットとして"生まれ変わった"場所です。
以前のこの一帯は「四四兵工場」という武器工場で働いていた軍人たちとその家族のために政府が準備した村でした。「四四南村」という名称は、かつての武器工場の名にちなんでいるのです。
軍人の家族たちが暮らした民家を改装した「眷村文物館」では、漫画のサザエさんに出てくるような電化製品(鍋)や日用品(デッキブラシ)などが"台湾の歴史を記録する"という目的で展示されています。不穏な懐かしさがこみあげてきます。それらは私が子どもの頃に大伯父や祖父母の家で見かけたものによく似ていました。おそらく私の両親が子ども時代に暮らした家の中にも、こんな日用品があったのでしょう。"歴史"と呼ぶには、近すぎる。距離感がゆがむような独特の戸惑いを覚えずにいられませんでした。
文物館を見学後、私はふらふらと併設されているカフェ――同じく民家を改装したもの――に入ります。代官山や下北沢にもありそうな洒落たそのカフェは、学生と思われる台湾の若いひとたちでおおいに賑わっていました。私もカフェの片隅に陣取ります。
――どこに行ったのだろう?
胸の中で、その疑問が徐々に募ります。
ここが、大陸の故郷に帰る日を夢見ながら台湾での日々を1日また1日と重ねたひとびとの住処を再開発した場所というのはよくわかりました。
――でも、ここが、こんなふうになってしまって、そのひとたちは、今、どこにいるの?
ボサノヴァらしき軽やかな心地よい音楽の流れる中、隣の席でははつらつとした声でボーイフレンドに語り掛けている女の子の中国語が聞こえます。後ろのほうでは、やはり若い男の子ふたりが互いにからかいあうような会話を楽しそうに交わしています。
平日の午後でした。日本人らしい観光客は見かけません。今、賑わっているカフェにいるひとたちの大半はおそらく台湾生まれの台湾人なのでしょう。
でも、かれやかのじょたちの祖父や曾祖父は、大陸で生まれたのかもしれない。武器工場で働きながら妻や子を養ったひともいるのかもしれない。いつの日か故郷に帰れるのを願いながら暮らし続けた仮の家を追い出され、晩年は子や孫のマンションに居候したかもしれない・・・・・・。
そんなことを身勝手に想像しながら私は、こんなところで巴樂汁(グァバジュース)を啜る自分は台湾のことをどれだけ知っているのだろう、と奇妙な後ろめたさをおぼえてきりりと胸が痛みます。
散歩中に見つけたジュースやお茶などの飲み物を売るお店の看板。「人生っていいお茶みたいなぁ」の日本語にほっこりした。
散歩はおとなの証拠とばかりに台湾を自由に歩きまわるようになったものの、両親の庇護の下では決して見えなかった"台湾"が垣間見えるたび、私はかえって台湾のことがわからなくなるような思いを抱きます。そう、台湾のことをもっと知ろうと思えば思うほど、それが一筋縄ではいかないということを思い知らされて、迷子の心地になるばかりなのです。むしろ私は、台湾の複雑な豊かさを身をもって味わいたくて、あえて迷子になるために散歩をしているのかもしれません。
温又柔 Twitter https://twitter.com/wenyuju





