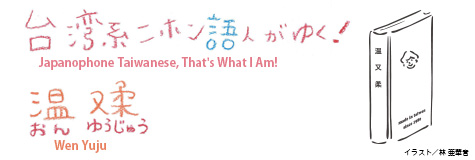
11.土地と声をめぐって
――台湾系ニホン語人はいつまでも揺れている――
満月から2日ほど過ぎた夜でした。空に浮かぶ月が、いつもよりも間近に迫って見えて、どきっとしました。車から降りると、空気は刺すように冷たく、地面には凍った雪が残っています。青森は寒い寒いと覚悟していたから、ちゃんと空に見惚れる余裕はありました。
お月さまだけではない。
星も、間近に迫ってきます。一粒一粒が煌々と輝いているのを感じます。ふだん自分の見ている空はずいぶん遠くにあるんだなあと思わずにいられません。
さあこちらに、とうながされて向かったのが「八戸ブックセンター」。八戸市が"公共事業"としてスタートさせたばかりの「町の本屋さん」です。
磨かれたガラス張りの入口から中に足を一歩踏み入れると、店内にはほんのりとコーヒーの良い香りが漂っていました。床板の色が明るく、天井が高いので、とてものびやかな心地になります。そんな開放的な空間に、それを眺めるひとたちが押し合いへし合いせずに済むように十分なゆとりをもって書架が配されています。
著者名の五十音順ではなく、さまざまなテーマ――「みわたす」「かんがえる」「よのなか」「どう生きるか」等々――に沿って並べられた本を長時間見入っているお客さんも多いとか。
重要なのは、ここが立ち読み禁止どころか、未購入の本でも書架と書架の間を縫って配置された椅子やソファーにすわって試し読みするのが可能というところ。しかも椅子やソファーのアームにはコーヒーカップ用のホルダーがついていて、飲食可能という仕様です。くつろぎながら本を読む場所のみならず、読書会を行うための「読書会ルーム」そして、執筆を希望するひとのための「カンヅメブース」と名づけられたコーナーもまた魅惑的でした。
でも、私をもっとも興奮させたのは、何よりもハンモックでした。
公園の遊具では何よりもブランコが好きな私は、ハンモックでひねもすのたりのたりと過ごすのが夢です。でも、なかなかハンモックとお目にかかれる機会はありません。
それがなんと八戸ブックセンターにはハンモックに揺られながら読書ができるコーナーがあるのです。
しかも、空いていればだれでも乗っていいという。
もちろん私も嬉々と乗りました。
乗り心地は最高でした。
こんなふうに揺れながら、お気に入りの長編小説をじっくりと読めるのなら、きっと幸せだろうなと思いました。でも途中でうつらうつらしそうです。

ハンモックにたちまち魅了される。読書の途中でうつらうつらしてしまいそうな心地よさ!
・・・・・・とまあ店内をこんなふうに案内してもらいながら、八戸ブックセンターとは、本を求め、本を読み、本を楽しみ、愛おしむひとたちが、自分自身の世界を深く掘り下げる場所なのだと感じました。
さらにいえば、本をめぐってひととひとが出会う交錯地点にもなるのだろうな、とも。
実は私は、小説家の石田千さん、詩人の管啓次郎さんと一緒に、このブックセンターのオープニング記念イベントに参加するためにやってきたのでした。
私たちをここまでみちびいてくれたのは木村友祐さんです。
八戸が舞台となった『海猫ツリーハウス』という木村さんの作品をはじめて読んだときのことは忘れられません。著者の地元でもある八戸のひとたちが交わす会話は、いわゆる標準語ではありませんでした。木村さんは、主に会話文の部分で濁音を多用しながら、南部弁と呼ばれる八戸という土地で話されていることばを、自分の小説に存分に取り込んでいました。そこには、標準語に「翻訳」するとこぼれ落ちたであろう熱気があふれていました。
『海猫ツリーハウス』が単行本化される際、早々と書評を書いたのが管啓次郎さんでした。曰く「音を知らないので、その訛りを再現することはできない。だがそこに、どこか心が浮きたつような魅力を感じる。音声が初めて文字になるとき、それを文字として記録する者の、精神の緊張と勇気を感じるからか」。
木村さん自身は、第33回すばる文学賞受賞者インタビューでこう語っていました。
「世の中は東京主導で動いているように見えるけど、今この同じ時間、田舎でも人はちゃんと生きている、声にならない叫びをあげている。そういう誰も知らない場所であがる声を聞きとりたい、すくい取っていきたい」
インタビュー記事を読みながら、このひとに会いたい、話がしてみたいという思いが募りました。というのも私もまた、カタカナを駆使して台湾語の響きをあらわしたり、漢字は漢字でも中国式の簡体字や台湾風の繁体字によって中国語の存在感を文中に示したりすることで、日本育ちの台湾人としての自分自身の言語経験を書いた「好去好来歌」と題した小説で第33回すばる文学賞の佳作をもらったばかりだったのです。
まもなく私の願いは叶い、木村さんと友だちになれました。
その後、私がもたもたと小説を書きあぐねる間も、木村さんは『聖地Cs』に『イサの氾濫』、そして『野良ビトたちの燃え上がる肖像』と、いまの日本社会のしくみや、弱きものを真っ先に押しつぶそうとする世の在り方を鋭く問う作品を次々と発表してきました。
2013年からは管啓次郎さんのお誘いで演出家の高山明さんによる観客参加型演劇作品「東京ヘテロトピア」のテキスト執筆陣に一緒に加わったり、そこから生まれた「鉄犬ヘテロトピア文学賞」などに関わりながら、お互いの創作に関する最も大事な動機を分かち合いながら過ごす機会にたくさん恵まれました。
管さんの表現を拝借すれば「文字の領域に音を引き込む試みや、書かれたことのないものを書きたいという気持ち」を持ちながらそれぞれの場所で習作にいそしんできた木村さんと自分とが、時を同じくして小説家として本格的なスタートを切ったことが、今となれば少なくとも私にとってはちょっとした運命だったように思えてなりません。
ふと、私の頭の中にあるフレーズが浮かんできます。
「いつまでもゆれている」
それは、管さんが『海猫ツリーハウス』に寄せた書評のタイトルなのでした。
その管さんたちとともに木村さんが待つ八戸に到着した翌日、いよいよ八戸ブックセンターオープニング記念イベントが始まります。
第1部のワークショップでは、管さんと石田さん、木村さんと私とふたつのグループに分かれて読者の方々と交流しました。受講者である10名の方が、事前に私の小説『来福の家』を読んでくださっているという前提で、それは始まりました。八戸市近郊(中には青森市から来てくださった方もいました!)に住む読書好きの方々が、私の書いたことを読んで感じたことを真摯に語る声に耳を傾けるうちに、1冊の本の作者にとってこれは何と贅沢な時間なのだろうという感動がだんだんとこみあげてきます。

管さん(後列右から3人目)、木村さん(前列左端)、石田さん(前列右端)、そして八戸ブックセンターのスタッフの方たちと。私のポーズは八戸の「八」。
参加者の中で最年少だったのは、八戸工業大学の男子学生でした。
彼は、ぼくは本を読むとき自分ならどうなのだろうと思うのですが、と遠慮がちに前置きしてからこう述べました。
「日本人なのか、台湾人なのか。主人公は、自分がナニジンなのかわからない。もしも自分がこんな境遇にいたら、たぶん押しつぶされると思う」
押しつぶされる。
率直なその表現に、なつかしい狂おしさが私の胸によみがえります。
「好去好来歌」の原稿を書いていた頃の私は、まさに、押しつぶされそうな思いで日々を過ごしていました。毎晩、パソコンに向かってひたすらことばを打ち続けながら、自分がここにいるという実感をつかもうともがいていました。たぶん私にとっての書くという行為は、ちゃんと自分はここにいると確かめるためにあったのです。
書いているときだけは、何にも押しつぶされずにいられる気がした。だから私には文学が必要だった。文学とはそれほど包容力のあるものなんです、と、大学生の彼をはじめ、ワークショップの参加者たちに向かって話しながら、たぶんいつかの自分自身に対してこの"真実"を私は伝えたいのだなと感じていました。
第1部のワークショップが終わったあとは、管さん、石田さんと合流して土地と声をめぐるトークイベントを行います。次の会場に移動しながら、木村さんがぽろっと言います。
「このブックセンターが、出口を探す心の駆け込み寺になるといいなと思うんです」
ほんとうにそうだなあ、と思いました。
文学には、人生の中に居場所をみつけられずにうろたえる心を支え、包み込み、ここにいてもいいと感じさせる力が備わっている。文学の入口が本である限り、これからも、ひとが本と出会うための場所は必要とされるはずだと私は思っています。
だからこそ、市をあげて、本とひとが繋がるための拠点を作り、育てて行こうと奮闘する八戸ブックセンターの関係者の方々の切実な思いが、たとえこれから長い時間がかかってでもきちんと報われるようにと願わずにはいられません。
第2部のトークイベントには約70名の方々が足を運んでくださいました。
冒頭では、管さん、石田さん、木村さん、私の4人でまずはそれぞれ「土地と声」をテーマに書き下ろした作品を朗読しました。
私は「ムゥーイの誘惑」と名づけたテキストを読みました。
種明かしすると、「ムゥーイ」とは「母語」を中国語で読んだときの音です。「母国語」が所属する国家を前提とした言語であるなら、そこから「国」が外れた「母語」はもっと原初的なもの。赤ん坊が母親や、母親代わりのおとなから聞かされることばのこと。
だから私の母語(ムゥーイ)は、中国語と台湾語がふんだんに織り交ざったニホン語なのです。
八戸に行くにあたって私は、もっと大胆に、母語(ムゥーイ)とは、だれに押し付けられたものでもなく、そのひと自身のことばを意味することば、と解釈しました。
たとえば、標準語に置き換えたら消滅しかねないリアリティや、熱を伴う土地のことば。そういった、土地から切り離しようのないことばが、日本じゅうのあちらこちらでいまこの瞬間も確かに響き合っているはずだ。
「翻訳したり、標準化されるとこぼれ落ちてしまうものの中にこそ、大事なものがある気がする」
いつかのインタビュー記事にあった木村さんのことばです。
ずっと東京にいるとどうしても忘れがちなことなのだけれど、日本も、日本語も、決して単一的なものではありません。私たちが思うよりもそれは幅があって、豊かな奥行きがあるものなのです。
私は、木村さんや仲間たちのムゥーイを育んだ八戸で、はちのへ、ではなく、はぢのへ、と発音するのをそっと真似てみます。
はぢのへ、はぢのへ。
自分のニホン語の中にあたらしい息吹が注ぎ込まれるのを感じて、胸がときめきました。もっと勇気が湧いたら、うんうん、とうなずく代わりに、んだんだ、とも言ってみたかったのだけれど、ちょっと照れくさくて今回は諦めました。
そんなふうに八戸の夜は更けていきました。
旅先で過ごす最終日にはいつもそうであるように、ひとりになったあとも私は旅を反芻しながら夜更かししていました。私の手元には「土地と声」と題された小冊子があります。管さん、石田さん、木村さん、私が綴ったテキストにそれぞれ呼応する素敵なイラストは、八戸ブックセンターの主要スタッフでもある森花子さんが描き下ろしてくださいました。

「土地と声」をテーマに書き下ろした「ムゥーイの誘惑」。森花子さんが寄せてくださった絵が愛らしい!
ホテルのシングルベッドに寝そべりながら、私は「はなれて、だまって」と名づけられた石田さんの文章を読みます。
「さいしょの呼吸で、たくさんの時間がうごめく。いたところといるところが、からだの中をくまなくめぐり、出会い、はなれていく。まえのめりに耳をかたむけなくても、あしたの天気を気にしなくても、地図をひろげて指でなぞらなくてもいい。土地も声も、すぐそばどころか、もう五臓六腑におさまろうとしている」
つい先ほどまで一緒だった石田さんの、やわらかい声を思いだしながら、目で指で、ひたひたとしみいる文章を味わうのは至福のひとときでした。そうするうちにブックセンターのハンモックに揺られていた心地もよみがえります。
次こそ、ウミネコの鳴き声を聞きに来よう。本屋さんのひとたちにも、木村さんが引き合わせてくれたチャーミングな町のひとたちにも、いつかまた会いたい。
そう思いながら、こんなふうに好きな町がこころの中に増えてゆく幸せに浸ります。
八戸はもう夜明け間近でした。日本最大級の館鼻岸壁朝市をおとずれるのは諦めて、次回、また来る口実にしようなどと思いながら幸福な興奮をどうにかしずめようと目をつむります。
私ときたら、自分の中でざわめくものをどうにか言葉にしたくていつもじたばたしているけど、たまには家を離れて、別の土地に身をおいて、耳を目を心を、めいっぱい開き、そうやって流れ込むものと合流して、合流させて、自分の輪郭を柔らかく拡げてゆかなくちゃなあ・・・・・・としみじみ思ううちに眠りに落ちます。
さて、今回はずいぶんと長くなってしまいました。
実は「台湾系ニホン語人がゆく!」はこれが最終回なのです。
ここでいったんお別れを告げなくてはなりません。ひとつに束ねられない日本、そして台湾のあちこちを行き来しながら、私は私のニホン語をこれからも育てます。その心は"いつまでもゆれている"。
これからも、どこかで、きっと会えるはず!
【Information】
2017年1月14日(土) 13:00~15:00 日中学院にて「私が中国語と仲良くなるまで」と題して講演。
https://www.rizhong.org/wp/wp-content/uploads/2016/12/kouenkai1.14.pdf
温又柔 Twitter https://twitter.com/wenyuju


